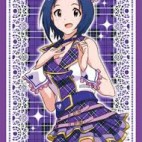2022/1/25 mtgの禁止制限改訂
2022年1月26日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
スタンダード
禁止 アールンドの天啓・ゼロ除算・不詳の安息地
ヒストリック
禁止 記憶の欠落
再調整および禁止解除 時を解す者、テフェリー
スタンダードとヒストリックはプレイしてないので、コメントは控えることにしました。
レガシー
禁止 敏捷なこそ泥、ラガバン
特に気になった点
>Magic Onlineのリーグのデータでは「青赤デルバー」の非ミラーマッチでの勝率は56%を超え、過去数週間に次点のアーキタイプの2倍以上のトロフィーを獲得しました。
>《目くらまし》や《意志の力》のバックアップを受けた序盤の《敏捷なこそ泥、ラガバン》による雪だるま式ゲームの傾向についての議論を耳にしました。高パワー・レベルで高効率のレガシーのカード・プールによって、序盤のマナとカードのアドバンテージは他のフォーマットよりもさらにゲームを決めてしまいます。
→先攻1ターン目にラガバンを出された後、返しに除去が手札にこないか、除去を撃っても目くらましor意志の力あたりで弾かれたりしたら2ターン目の攻撃でアドバンテージを稼がれてしまう上に、宝物トークンのせいで色拘束をある程度無視でき、おまけに2マナ払っての疾駆で隙をついて殴ることもできると1マナのクリーチャーとしては問題がありすぎたので、禁止になったのは当然だと思いました。
(前の大会で青緑スタイフルノートで挑んだ際、除去できなかったせいでドローソースどころか森の知恵まで盗られて負けたので「早く禁止になってくれ」と思うほどでした。高い上に禁止になりそうだったので1枚も持ってませんし)
モダンでラガバンが禁止にならなかったのは、レガシーよりはマナコストが大きいカードが使われやすい上に、目くらましが存在しないというのが一番大きい気がしました。
(否定の力は存在しますが、自分のターンには撃てない上に、激情などのクリーチャーによる除去からは守ってくれないのが気になったか)
個人的には、モダンで大暴れしているウルザの物語が禁止にならなかったことを疑問に思いました。
(理由を考えるとしたら、既にトロンが存在するため土地対策がサイドに入ることが多く、エンチャント破壊・高山の月・血染めの月・広がりゆく海で墓地に送れるという欠点があるところか)
さすがに不毛が存在するレガシーで禁止になるとは思えないので、モダンで禁止になって安くなったら4枚揃えようと思います。
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0035744/
スタンダード
禁止 アールンドの天啓・ゼロ除算・不詳の安息地
ヒストリック
禁止 記憶の欠落
再調整および禁止解除 時を解す者、テフェリー
スタンダードとヒストリックはプレイしてないので、コメントは控えることにしました。
レガシー
禁止 敏捷なこそ泥、ラガバン
特に気になった点
>Magic Onlineのリーグのデータでは「青赤デルバー」の非ミラーマッチでの勝率は56%を超え、過去数週間に次点のアーキタイプの2倍以上のトロフィーを獲得しました。
>《目くらまし》や《意志の力》のバックアップを受けた序盤の《敏捷なこそ泥、ラガバン》による雪だるま式ゲームの傾向についての議論を耳にしました。高パワー・レベルで高効率のレガシーのカード・プールによって、序盤のマナとカードのアドバンテージは他のフォーマットよりもさらにゲームを決めてしまいます。
→先攻1ターン目にラガバンを出された後、返しに除去が手札にこないか、除去を撃っても目くらましor意志の力あたりで弾かれたりしたら2ターン目の攻撃でアドバンテージを稼がれてしまう上に、宝物トークンのせいで色拘束をある程度無視でき、おまけに2マナ払っての疾駆で隙をついて殴ることもできると1マナのクリーチャーとしては問題がありすぎたので、禁止になったのは当然だと思いました。
(前の大会で青緑スタイフルノートで挑んだ際、除去できなかったせいでドローソースどころか森の知恵まで盗られて負けたので「早く禁止になってくれ」と思うほどでした。
モダンでラガバンが禁止にならなかったのは、レガシーよりはマナコストが大きいカードが使われやすい上に、目くらましが存在しないというのが一番大きい気がしました。
(否定の力は存在しますが、自分のターンには撃てない上に、激情などのクリーチャーによる除去からは守ってくれないのが気になったか)
個人的には、モダンで大暴れしているウルザの物語が禁止にならなかったことを疑問に思いました。
(理由を考えるとしたら、既にトロンが存在するため土地対策がサイドに入ることが多く、エンチャント破壊・高山の月・血染めの月・広がりゆく海で墓地に送れるという欠点があるところか)
さすがに不毛が存在するレガシーで禁止になるとは思えないので、モダンで禁止になって安くなったら4枚揃えようと思います。
2021/2/15 mtgの続唱のルール変更と禁止制限改訂
2021年2月19日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
続唱のルール変更について
>あなたがこの呪文を唱えたとき、あなたのライブラリーの一番上のカードを、点数で見たマナ・コストがこの呪文より低い土地でないカードが取り除かれるまで追放する。その点数で見たマナ・コストがその呪文の点数で見たマナ・コストよりも小さいなら、あなたはそのカードをそのマナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。その後、これにより追放されて唱えられなかったすべてのカードを、あなたのライブラリーの一番下に無作為の順番で置く。
→専用構築をすれば、3マナの続唱呪文(モダンなら暴力的な突発や献身的な嘆願、レガシーならそれに加えて断片無き工作員も)を唱えただけで7マナの星界の騙し屋、ティボルトを出せるのは流石にどうかと思ったので、このルール変更は当然だと思いました。
(個人的には、カルドハイムで嘘の神、ヴァルキーが出た時点ではそんなことができると思ってなかったので、できると知った時にはびっくりしました。あと、嘘の神、ヴァルキーが禁止にされなかったのは良しとすべきか)
禁止改定について
ヒストリック
禁止 自然の怒りのタイタン、ウーロ・創造の座、オムナス
パイオニア
禁止 地底街の密告人・欄干のスパイ・自然の怒りのタイタン、ウーロ・時を解す者、テフェリー・荒野の再生
ヒストリックもパイオニアもプレイしたことがないのでコメントは控えますが、強すぎるカードとコンボパーツに規制をかけたかったことだけは分かりました。
モダン
禁止 猿人の指導霊・自然の怒りのタイタン、ウーロ・ティボルトの計略・神秘の聖域・死者の原野
(猿人の指導霊)
>モダンのカードプールが広がったので、近年の「Oops! All Spells」や《ゴブリンの放火砲》系デッキ、《ティボルトの計略》デッキの一部など、手札から初期に勝利するコンボを組み上げられるデッキの可能性も出ています。
>この種類のコンボデッキを全体として低速化し、序盤戦でも対戦相手に対応したプレイの準備をする時間を与えるようにするため、《猿人の指導霊》を禁止します。
→「高速コンボデッキを低速化させるため」禁止にするなら、「なぜ今更禁止にするのか?」と思いました。
(猿人の指導霊を使った高速コンボデッキなら、割と前からグリセルシュートやネオブランドが存在したので。これらは墓地対策や打ち消しに弱かったりするから良かったんでしょうか?)
(自然の怒りのタイタン、ウーロ)
>パイオニア同様、モダンでも《自然の怒りのタイタン、ウーロ》はいくつものトップデッキの支配的な常連になっており、他のミッドレンジやコントロール戦略にとって対抗するのが難しいパワーレベルにありました。
>メタゲームの中に様々なミッドレンジ戦略や他の遅いデッキが存在できる余地を作るため、モダンでも《自然の怒りのタイタン、ウーロ》を禁止します。
→ウーロが出た後、モダンの大会に1回しか出ていない私から見たら、動き出したらとても強いとはいえ、それまでに3マナ(ここで土地を1枚多くセット・3点ゲイン・1ドローがついてくる)→4マナ&墓地の5枚が必要とやや遅いと感じたので、禁止になるとは思ってませんでした。
しかし、墓地対策や追放でもしない限り何度でも蘇る可能性がある上に、動き出したら毎ターン土地を1枚多くセット・3点ゲイン・1ドローで莫大なアドバンテージを稼いでくれるのもあって「コントロールにはとりあえず入れておこう」といった感じになっていたような気がした(晴れる屋のデッキ検索を見て。1枚動き出せば勝てるためか、伝説かつ重めにも関わらず4枚積まれていたのもここで知った)ので、禁止になったのは当然だと思いました。
(まあ、レガシーでもオーコと組んで大暴れしていたぐらいなので、モダンで使えていいカードではないというのもあるでしょうが)
(ティボルトの計略)
>いくつものフォーマットにおける新しい《ティボルトの計略》デッキについての議論がありますが、私たちはモダンを、これらのデッキが《ティボルトの計略》と続唱との相互作用を経る場合にのみ問題なフォーマットだと考えています。
>このデッキの全体的な勝率は問題になるものではありませんが、モダンをプレイして面白くないものにするような、ゲームにならないゲームに寄与していると言えます。
>今回の更新の目標はメタゲームをもっと楽しい場所へ動かすことなので、《ティボルトの計略》デッキがメタゲーム内に残り続けることはその目標に反すると考えられます。
→ティボルトの計略がゲームを面白くないものにするというなら、なぜ地底街の密告人&欄干のスパイ・グリセルブランド・ゴブリンの放火砲あたりはノータッチなんでしょうか?
(勝率に問題がないなら、これだけを禁止にする理由はないと思うんですが)
(神秘の聖域&死者の原野)
>《自然の怒りのタイタン、ウーロ》に合わせて、ランプやコントロール戦略でよく使われていてゲームプレイのパターンの多様性を引き下げていると思われる土地2枚、《死者の原野》と《神秘の聖域》も抑制します。
>遅いゲームで反復的で双方向性のないゲームの局面を、これらの土地は比較的小さいデッキ構築上の制約で生み出します。
→前者はウーロと一緒にヴァラクート以外のコントロールの勝ち手段になる「土地」として採用されていたこと、後者はショックランドのおかげで島を3枚並べるのが難しくない上に、謎めいた命令の使い回しや終末の積み込みを「土地の能力で」行えてしまうのが問題視されたんでしょう。
(そして、モダンで禁止にされるほど強い死者の原野を全く評価してなかった、私の見る目の無さも浮き彫りに…既に明らかになってるだろと言ってはいけない)
レガシー
禁止 戦慄衆の秘儀術師・王冠泥棒、オーコ・アーカムの天測儀
(戦慄衆の秘儀術師)
>《戦慄衆の秘儀術師》は、すでに最強付近にある「ティムール・デルバー」などのカードや戦略をさらに強化する形の、強力でゲームを決めるものだとわかっています。
>《王冠泥棒、オーコ》がなければ、《戦慄衆の秘儀術師》戦略がさらに突出するだけでしょう。
>結局、私たちに届いたコミュニティの意見は、《戦慄衆の秘儀術師》はゲームプレイの最序盤を決定づけてしまい、対戦相手が即座にそれを除去できるかどうかだけで決まるゲームがあまりにも多くなるというものでした。
→戦慄衆の秘儀術師が禁止になったと知った時はすごく驚きましたが、ウィザーズは「攻撃を通し続けられたら思案・渦まく知識・稲妻・剣鍬といった強力な1マナの呪文を使い回してアドバンテージを稼げる能力」を持つ2マナのクリーチャーは強すぎたと判断したんでしょう。
(1/3というサイズのおかげで、2マナのサリアで討ち取ることができないのも、相手をしていた時は辛く感じました)
ターンが返ってくれば勝てるわけではないのに、禁止になったクリーチャーは(相棒を除き)レガシーでは死儀礼に続き2体目になりましたね…
(隠遁ドルイドとゴブリン徴募兵は、ターンが返ってくれば勝てる可能性が高いので除外で)
(王冠泥棒、オーコ)
>広大なカードプールがあるレガシーでは、とてつもない量のデッキ構築の選択肢があり、そして革新的なデッキ構築と調整による利益が与えられるべきです。
>そのカードパワーと柔軟性から、《王冠泥棒、オーコ》は想定外の脅威や防御に対してさえ簡単な回答になり、また一般にゲームプレイのパターンをフォーマットの精神に反する方向で均質化させてしまいます。
→3マナとプレインズウォーカーとしてはコストが軽いにも関わらず初期忠誠値が4もあり、ほとんどのクリーチャー&アーティファクトに+1能力であっさりと対処できる上に、+2能力と合わせてフィニッシャーにもなれるのは、レガシーでも許されなかったようです。
(これのせいでマーベリックを使う気が起きなくなったので、禁止になってくれたのはありがたかったです。ティムールデルバー相手に実物提示教育からのエムラで勝負を決めやすくなったのも、スニークショーにとっては追い風か)
(アーカムの天測儀)
>《アーカムの天測儀》は、レガシーのメタゲームでは特に重要な部分である、色の高い柔軟性とマナ妨害への高い耐性の両方を備えたマナ基盤を可能にします。
>結局、このような耐性を比較的低い投資で得られる少数のデッキの優位は、メタゲームの多様性を低めることを招くと考えられます。
→レガシーのデッキを安価で多色化するのに貢献していたので、禁止になったのは少しショックでしたが「基本氷雪土地をたくさん入れた4色以上のデッキ」のキーパーツであることを考えたら、禁止になったのは残念ながら当然だと思いました。
おまけ(自然の怒りのタイタン、ウーロ)
>レガシーで3~4マナの呪文に求められる水準は高く、《自然の怒りのタイタン、ウーロ》は競技的であっても支配的ではない選択肢として存在できると考えます。
>さらに、《王冠泥棒、オーコ》と《アーカムの天測儀》の禁止によって、《自然の怒りのタイタン、ウーロ》が当然に入る既存のデッキのメタゲーム比率は大きく下がることでしょう。
→思案・定業・渦まく知識が4枚入れられるレガシーでは、モダン以上に安定したコンボデッキが組める上に、動き出すのがやや遅いので「強いけど禁止にはならない」止まりになりそうです。
(とはいえ、とりあえず3マナで出しても悪くない上に、消耗戦に強いので暴れすぎたら禁止になるかも)
ヴィンテージ
禁止解除 夢の巣のルールス
>相棒のルールを変更して必要になった追加のマナは、ヴィンテージのパワーレベルという文脈では高すぎるほどの代償となりました。
→相棒として使えるとはいえ、手札に加えるのに3マナかかるのは結構痛いと思うので、再び禁止にする必要はないと思いました。
モダンやレガシーでこれだけの禁止カードが出たのを知って「ウィザーズは、本気でカードパワーを調整する気があるのか?」と思いました。
(オーコはスタン・パイオニア・モダン、ウーロはスタン、天測儀はモダンで既に禁止になっているのもあって)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034792/
続唱のルール変更について
>あなたがこの呪文を唱えたとき、あなたのライブラリーの一番上のカードを、点数で見たマナ・コストがこの呪文より低い土地でないカードが取り除かれるまで追放する。その点数で見たマナ・コストがその呪文の点数で見たマナ・コストよりも小さいなら、あなたはそのカードをそのマナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。その後、これにより追放されて唱えられなかったすべてのカードを、あなたのライブラリーの一番下に無作為の順番で置く。
→専用構築をすれば、3マナの続唱呪文(モダンなら暴力的な突発や献身的な嘆願、レガシーならそれに加えて断片無き工作員も)を唱えただけで7マナの星界の騙し屋、ティボルトを出せるのは流石にどうかと思ったので、このルール変更は当然だと思いました。
(個人的には、カルドハイムで嘘の神、ヴァルキーが出た時点ではそんなことができると思ってなかったので、できると知った時にはびっくりしました。あと、嘘の神、ヴァルキーが禁止にされなかったのは良しとすべきか)
禁止改定について
ヒストリック
禁止 自然の怒りのタイタン、ウーロ・創造の座、オムナス
パイオニア
禁止 地底街の密告人・欄干のスパイ・自然の怒りのタイタン、ウーロ・時を解す者、テフェリー・荒野の再生
ヒストリックもパイオニアもプレイしたことがないのでコメントは控えますが、強すぎるカードとコンボパーツに規制をかけたかったことだけは分かりました。
モダン
禁止 猿人の指導霊・自然の怒りのタイタン、ウーロ・ティボルトの計略・神秘の聖域・死者の原野
(猿人の指導霊)
>モダンのカードプールが広がったので、近年の「Oops! All Spells」や《ゴブリンの放火砲》系デッキ、《ティボルトの計略》デッキの一部など、手札から初期に勝利するコンボを組み上げられるデッキの可能性も出ています。
>この種類のコンボデッキを全体として低速化し、序盤戦でも対戦相手に対応したプレイの準備をする時間を与えるようにするため、《猿人の指導霊》を禁止します。
→「高速コンボデッキを低速化させるため」禁止にするなら、「なぜ今更禁止にするのか?」と思いました。
(猿人の指導霊を使った高速コンボデッキなら、割と前からグリセルシュートやネオブランドが存在したので。これらは墓地対策や打ち消しに弱かったりするから良かったんでしょうか?)
(自然の怒りのタイタン、ウーロ)
>パイオニア同様、モダンでも《自然の怒りのタイタン、ウーロ》はいくつものトップデッキの支配的な常連になっており、他のミッドレンジやコントロール戦略にとって対抗するのが難しいパワーレベルにありました。
>メタゲームの中に様々なミッドレンジ戦略や他の遅いデッキが存在できる余地を作るため、モダンでも《自然の怒りのタイタン、ウーロ》を禁止します。
→ウーロが出た後、モダンの大会に1回しか出ていない私から見たら、動き出したらとても強いとはいえ、それまでに3マナ(ここで土地を1枚多くセット・3点ゲイン・1ドローがついてくる)→4マナ&墓地の5枚が必要とやや遅いと感じたので、禁止になるとは思ってませんでした。
しかし、墓地対策や追放でもしない限り何度でも蘇る可能性がある上に、動き出したら毎ターン土地を1枚多くセット・3点ゲイン・1ドローで莫大なアドバンテージを稼いでくれるのもあって「コントロールにはとりあえず入れておこう」といった感じになっていたような気がした(晴れる屋のデッキ検索を見て。1枚動き出せば勝てるためか、伝説かつ重めにも関わらず4枚積まれていたのもここで知った)ので、禁止になったのは当然だと思いました。
(まあ、レガシーでもオーコと組んで大暴れしていたぐらいなので、モダンで使えていいカードではないというのもあるでしょうが)
(ティボルトの計略)
>いくつものフォーマットにおける新しい《ティボルトの計略》デッキについての議論がありますが、私たちはモダンを、これらのデッキが《ティボルトの計略》と続唱との相互作用を経る場合にのみ問題なフォーマットだと考えています。
>このデッキの全体的な勝率は問題になるものではありませんが、モダンをプレイして面白くないものにするような、ゲームにならないゲームに寄与していると言えます。
>今回の更新の目標はメタゲームをもっと楽しい場所へ動かすことなので、《ティボルトの計略》デッキがメタゲーム内に残り続けることはその目標に反すると考えられます。
→ティボルトの計略がゲームを面白くないものにするというなら、なぜ地底街の密告人&欄干のスパイ・グリセルブランド・ゴブリンの放火砲あたりはノータッチなんでしょうか?
(勝率に問題がないなら、これだけを禁止にする理由はないと思うんですが)
(神秘の聖域&死者の原野)
>《自然の怒りのタイタン、ウーロ》に合わせて、ランプやコントロール戦略でよく使われていてゲームプレイのパターンの多様性を引き下げていると思われる土地2枚、《死者の原野》と《神秘の聖域》も抑制します。
>遅いゲームで反復的で双方向性のないゲームの局面を、これらの土地は比較的小さいデッキ構築上の制約で生み出します。
→前者はウーロと一緒にヴァラクート以外のコントロールの勝ち手段になる「土地」として採用されていたこと、後者はショックランドのおかげで島を3枚並べるのが難しくない上に、謎めいた命令の使い回しや終末の積み込みを「土地の能力で」行えてしまうのが問題視されたんでしょう。
(そして、モダンで禁止にされるほど強い死者の原野を全く評価してなかった、私の見る目の無さも浮き彫りに…
レガシー
禁止 戦慄衆の秘儀術師・王冠泥棒、オーコ・アーカムの天測儀
(戦慄衆の秘儀術師)
>《戦慄衆の秘儀術師》は、すでに最強付近にある「ティムール・デルバー」などのカードや戦略をさらに強化する形の、強力でゲームを決めるものだとわかっています。
>《王冠泥棒、オーコ》がなければ、《戦慄衆の秘儀術師》戦略がさらに突出するだけでしょう。
>結局、私たちに届いたコミュニティの意見は、《戦慄衆の秘儀術師》はゲームプレイの最序盤を決定づけてしまい、対戦相手が即座にそれを除去できるかどうかだけで決まるゲームがあまりにも多くなるというものでした。
→戦慄衆の秘儀術師が禁止になったと知った時はすごく驚きましたが、ウィザーズは「攻撃を通し続けられたら思案・渦まく知識・稲妻・剣鍬といった強力な1マナの呪文を使い回してアドバンテージを稼げる能力」を持つ2マナのクリーチャーは強すぎたと判断したんでしょう。
(1/3というサイズのおかげで、2マナのサリアで討ち取ることができないのも、相手をしていた時は辛く感じました)
ターンが返ってくれば勝てるわけではないのに、禁止になったクリーチャーは(相棒を除き)レガシーでは死儀礼に続き2体目になりましたね…
(隠遁ドルイドとゴブリン徴募兵は、ターンが返ってくれば勝てる可能性が高いので除外で)
(王冠泥棒、オーコ)
>広大なカードプールがあるレガシーでは、とてつもない量のデッキ構築の選択肢があり、そして革新的なデッキ構築と調整による利益が与えられるべきです。
>そのカードパワーと柔軟性から、《王冠泥棒、オーコ》は想定外の脅威や防御に対してさえ簡単な回答になり、また一般にゲームプレイのパターンをフォーマットの精神に反する方向で均質化させてしまいます。
→3マナとプレインズウォーカーとしてはコストが軽いにも関わらず初期忠誠値が4もあり、ほとんどのクリーチャー&アーティファクトに+1能力であっさりと対処できる上に、+2能力と合わせてフィニッシャーにもなれるのは、レガシーでも許されなかったようです。
(これのせいでマーベリックを使う気が起きなくなったので、禁止になってくれたのはありがたかったです。ティムールデルバー相手に実物提示教育からのエムラで勝負を決めやすくなったのも、スニークショーにとっては追い風か)
(アーカムの天測儀)
>《アーカムの天測儀》は、レガシーのメタゲームでは特に重要な部分である、色の高い柔軟性とマナ妨害への高い耐性の両方を備えたマナ基盤を可能にします。
>結局、このような耐性を比較的低い投資で得られる少数のデッキの優位は、メタゲームの多様性を低めることを招くと考えられます。
→レガシーのデッキを安価で多色化するのに貢献していたので、禁止になったのは少しショックでしたが「基本氷雪土地をたくさん入れた4色以上のデッキ」のキーパーツであることを考えたら、禁止になったのは残念ながら当然だと思いました。
おまけ(自然の怒りのタイタン、ウーロ)
>レガシーで3~4マナの呪文に求められる水準は高く、《自然の怒りのタイタン、ウーロ》は競技的であっても支配的ではない選択肢として存在できると考えます。
>さらに、《王冠泥棒、オーコ》と《アーカムの天測儀》の禁止によって、《自然の怒りのタイタン、ウーロ》が当然に入る既存のデッキのメタゲーム比率は大きく下がることでしょう。
→思案・定業・渦まく知識が4枚入れられるレガシーでは、モダン以上に安定したコンボデッキが組める上に、動き出すのがやや遅いので「強いけど禁止にはならない」止まりになりそうです。
(とはいえ、とりあえず3マナで出しても悪くない上に、消耗戦に強いので暴れすぎたら禁止になるかも)
ヴィンテージ
禁止解除 夢の巣のルールス
>相棒のルールを変更して必要になった追加のマナは、ヴィンテージのパワーレベルという文脈では高すぎるほどの代償となりました。
→相棒として使えるとはいえ、手札に加えるのに3マナかかるのは結構痛いと思うので、再び禁止にする必要はないと思いました。
モダンやレガシーでこれだけの禁止カードが出たのを知って「ウィザーズは、本気でカードパワーを調整する気があるのか?」と思いました。
(オーコはスタン・パイオニア・モダン、ウーロはスタン、天測儀はモダンで既に禁止になっているのもあって)
2020/10/12 mtgの禁止制限改訂
2020年10月14日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
スタンダード
禁止 創造の座、オムナス・幸運のクローバー・僻境への脱出
ヒストリック
禁止 時を解す者、テフェリー・荒野の再生
一時停止 創造の座、オムナス
一時停止解除 炎樹族の使者
ブロール
禁止 創造の座、オムナス
最近の禁止改訂を見ていたら「スタンダードでトップレア(他の例:オーコ・ウーロ)がことごとく禁止になったのに対しては訴訟の話すら出てこないのに、なぜ再録禁止カードが再録されるとなると訴訟に発展するんだろう?」と思いました。
(再録禁止カードが再録されても価値こそ下がれど使えなくなるわけではないのに、禁止カードになったら最悪ただの紙切れになってしまうのもあって。「ウィザーズの信用を落とす」という点で考えたら、スタンでの禁止カード連発の方が遥かにダメージが大きいでしょうに)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034476/
スタンダード
禁止 創造の座、オムナス・幸運のクローバー・僻境への脱出
ヒストリック
禁止 時を解す者、テフェリー・荒野の再生
一時停止 創造の座、オムナス
一時停止解除 炎樹族の使者
ブロール
禁止 創造の座、オムナス
最近の禁止改訂を見ていたら「スタンダードでトップレア(他の例:オーコ・ウーロ)がことごとく禁止になったのに対しては訴訟の話すら出てこないのに、なぜ再録禁止カードが再録されるとなると訴訟に発展するんだろう?」と思いました。
(再録禁止カードが再録されても価値こそ下がれど使えなくなるわけではないのに、禁止カードになったら最悪ただの紙切れになってしまうのもあって。「ウィザーズの信用を落とす」という点で考えたら、スタンでの禁止カード連発の方が遥かにダメージが大きいでしょうに)
2020/8/3 mtgの禁止制限改訂
2020年8月7日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
スタンダード
禁止 荒野の再生・成長のらせん・時を解す者、テフェリー・大釜の使い魔
パイオニア
禁止 真実を覆すもの・隠された手、ケシス・歩行バリスタ・死の国からの脱出
ヒストリック
一時停止 荒野の再生・時を解す者、テフェリー
ブロール
禁止 時を解す者、テフェリー
どのフォーマットも現在はプレイしてないのでコメントは控えますが、スタン・ヒストリック・ブロールでのテフェリーと、パイオニアでの真実を覆すものとバリスタの禁止は、特に金銭的ダメージが大きかったでしょうね…
(というか、プレイ人口が多いはずのスタンで禁止カードが10枚もあるのはさすがに問題では?)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034244/
スタンダード
禁止 荒野の再生・成長のらせん・時を解す者、テフェリー・大釜の使い魔
パイオニア
禁止 真実を覆すもの・隠された手、ケシス・歩行バリスタ・死の国からの脱出
ヒストリック
一時停止 荒野の再生・時を解す者、テフェリー
ブロール
禁止 時を解す者、テフェリー
どのフォーマットも現在はプレイしてないのでコメントは控えますが、スタン・ヒストリック・ブロールでのテフェリーと、パイオニアでの真実を覆すものとバリスタの禁止は、特に金銭的ダメージが大きかったでしょうね…
(というか、プレイ人口が多いはずのスタンで禁止カードが10枚もあるのはさすがに問題では?)
2020/7/13 mtgの禁止制限改訂
2020年7月15日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
ヒストリック
禁止 裏切りの工作員・軍団のまとめ役、ウィノータ・創案の火・運命のきずな
一時停止 炎樹族の使者
パイオニア
禁止解除 ニッサの誓い
パウパー
禁止 探検の地図・神秘の聖域
以上のフォーマットの禁止カードについては、一度もプレイしたことがないためノーコメントで
モダン
禁止 アーカムの天測儀
特に気になった点
>ここ数ヶ月のモダンのメタゲームでは、《アーカムの天測儀》を使った多色デッキの使用率と勝率の上昇が見られ、いくつかのバリエーションを含めてミラーマッチ以外のマッチの勝率が55%に近づいています。
>メタゲームの中に多色の「グッドスタッフ」デッキの居場所があることは本質的に悪いことではありませんが、その強さと柔軟性は通常マナ基盤の妥協をすることによって相殺されており、タップ状態で戦場に出たり、ライフを支払ったりする土地を使うこと、その他のデッキ構築面での制限がかかったりすることがよくあります。
>《アーカムの天測儀》はその代償をあまりにも安いものにしてしまい、1枚の《アーカムの天測儀》がカード1枚分のリソースを使うことなく出た後のそのゲームのマナ基盤を素晴らしいものにしてしまうことがよくあります。
→基本氷雪土地を入れる必要こそあるものの、その条件も基本土地が入らないようなデッキでない限りは容易に達成できるうえに、一度出してしまえば基本氷雪土地とこれだけで3・4色のデッキを回せるというのは、さすがにマナ基盤の安定性が高すぎたということでしょうか?
(高速で出されなければ、血染めの月すらほぼ無効化してしまえますし)
>さらに、《アーカムの天測儀》の軽いアーティファクト・パーマネントであるという長所は他のシナジーを生み出し、カード・アドバンテージのために明滅したり再利用したりすることができます。
→氷雪なので氷河のコアトルの接死付与に貢献でき、ゴブリンの技師の効果のコストにして墓地に落ちた(または、技師の効果で落とした)罠の橋や飛行機械の鋳造所などを釣り上げられるアーティファクトを「氷雪1マナで」「アドバンテージを失うことなく」出せるのはモダンでは問題だったと判断したんでしょう。
(基本土地が入らないクロックパーミッション・1マナのカードを入れづらいストンピィ系のデッキには入らないものの、同じ理由でレガシーで禁止にされてもおかしくはない気がしてきました)
最近はモダンをプレイしていないとはいえ、貧乏デッキのマナ基盤の安定にも大きく貢献してきたであろうアーカムの天測儀が禁止になったのはちょっとだけショックでした。
(とはいえ、3・4色のデッキを「血染めの月の影響を受けずに」回すのに貢献するアーティファクトを、「アドバンテージを失わずに」「1マナで出せる」のが問題だと言われたら否定はできませんが)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034150/
ヒストリック
禁止 裏切りの工作員・軍団のまとめ役、ウィノータ・創案の火・運命のきずな
一時停止 炎樹族の使者
パイオニア
禁止解除 ニッサの誓い
パウパー
禁止 探検の地図・神秘の聖域
以上のフォーマットの禁止カードについては、一度もプレイしたことがないためノーコメントで
モダン
禁止 アーカムの天測儀
特に気になった点
>ここ数ヶ月のモダンのメタゲームでは、《アーカムの天測儀》を使った多色デッキの使用率と勝率の上昇が見られ、いくつかのバリエーションを含めてミラーマッチ以外のマッチの勝率が55%に近づいています。
>メタゲームの中に多色の「グッドスタッフ」デッキの居場所があることは本質的に悪いことではありませんが、その強さと柔軟性は通常マナ基盤の妥協をすることによって相殺されており、タップ状態で戦場に出たり、ライフを支払ったりする土地を使うこと、その他のデッキ構築面での制限がかかったりすることがよくあります。
>《アーカムの天測儀》はその代償をあまりにも安いものにしてしまい、1枚の《アーカムの天測儀》がカード1枚分のリソースを使うことなく出た後のそのゲームのマナ基盤を素晴らしいものにしてしまうことがよくあります。
→基本氷雪土地を入れる必要こそあるものの、その条件も基本土地が入らないようなデッキでない限りは容易に達成できるうえに、一度出してしまえば基本氷雪土地とこれだけで3・4色のデッキを回せるというのは、さすがにマナ基盤の安定性が高すぎたということでしょうか?
(高速で出されなければ、血染めの月すらほぼ無効化してしまえますし)
>さらに、《アーカムの天測儀》の軽いアーティファクト・パーマネントであるという長所は他のシナジーを生み出し、カード・アドバンテージのために明滅したり再利用したりすることができます。
→氷雪なので氷河のコアトルの接死付与に貢献でき、ゴブリンの技師の効果のコストにして墓地に落ちた(または、技師の効果で落とした)罠の橋や飛行機械の鋳造所などを釣り上げられるアーティファクトを「氷雪1マナで」「アドバンテージを失うことなく」出せるのはモダンでは問題だったと判断したんでしょう。
(基本土地が入らないクロックパーミッション・1マナのカードを入れづらいストンピィ系のデッキには入らないものの、同じ理由でレガシーで禁止にされてもおかしくはない気がしてきました)
最近はモダンをプレイしていないとはいえ、貧乏デッキのマナ基盤の安定にも大きく貢献してきたであろうアーカムの天測儀が禁止になったのはちょっとだけショックでした。
(とはいえ、3・4色のデッキを「血染めの月の影響を受けずに」回すのに貢献するアーティファクトを、「アドバンテージを失わずに」「1マナで出せる」のが問題だと言われたら否定はできませんが)
詳しくはこちら
全フォーマットで禁止
Invoke Prejudice(ネオナチを連想させるらしい)、Cleanse(民族浄化を連想させるそうな)、Stone-Throwing Devils(イスラム教での、「悪魔への投石」と呼ばれる宗教的儀式を揶揄したからだそうで)、プラデッシュの漂泊民(英語版のカード名に「ジプシー」という言葉を含むからだってさ)、Jihad(イスラム教での「ジハード」という言葉は、実際には「努力」という意味で、必ずしも軍事的要素を含むわけじゃないらしいんだけど、このカード内では「聖戦」だと解釈したそうで)、Imprison(カード内の黒人につけられていた金属製のマスクが、奴隷制時代の米国南部で、黒人奴隷の拘束・拷問に使われていたんだって)、十字軍(現実のそれで間違いないはず)
特に気になった点
>人種差別的要素は、私たちのゲームはもちろん、いかなる場所においても存在が許されるものではありません。
>ここ数週間に起きた出来事と現在進行形で交わされている「有色人種を支援するためにできること」についてのさまざまな意見を受け、私たちも私たち自身を省みて、私たちが取り組んできたことと取り組んでこなかったことを見つめ直しました。私たちの取り組みが不十分であるときに、そのことに気づかせてくださる皆さまには、心から感謝いたします。
→そう思っているなら、該当するカードの存在をなかったことにするのではなくて、上述のカードを挙げた上で「このような過ちを犯したことに深く反省すると共に、関係者と一緒になって再発防止に努めていく」といった声明文を発するに留めた方が、人種差別や文化侮辱への対処としては効果的なのではないかと思いました。
色々調べて思ったんですが、白人による黒人への差別にはよく触れられるのに、黒人による犯罪や韓国人による黒人への差別についてはそこまで触れられない気がするのは何故なんでしょうか?
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034052/
全フォーマットで禁止
Invoke Prejudice(ネオナチを連想させるらしい)、Cleanse(民族浄化を連想させるそうな)、Stone-Throwing Devils(イスラム教での、「悪魔への投石」と呼ばれる宗教的儀式を揶揄したからだそうで)、プラデッシュの漂泊民(英語版のカード名に「ジプシー」という言葉を含むからだってさ)、Jihad(イスラム教での「ジハード」という言葉は、実際には「努力」という意味で、必ずしも軍事的要素を含むわけじゃないらしいんだけど、このカード内では「聖戦」だと解釈したそうで)、Imprison(カード内の黒人につけられていた金属製のマスクが、奴隷制時代の米国南部で、黒人奴隷の拘束・拷問に使われていたんだって)、十字軍(現実のそれで間違いないはず)
特に気になった点
>人種差別的要素は、私たちのゲームはもちろん、いかなる場所においても存在が許されるものではありません。
>ここ数週間に起きた出来事と現在進行形で交わされている「有色人種を支援するためにできること」についてのさまざまな意見を受け、私たちも私たち自身を省みて、私たちが取り組んできたことと取り組んでこなかったことを見つめ直しました。私たちの取り組みが不十分であるときに、そのことに気づかせてくださる皆さまには、心から感謝いたします。
→そう思っているなら、該当するカードの存在をなかったことにするのではなくて、上述のカードを挙げた上で「このような過ちを犯したことに深く反省すると共に、関係者と一緒になって再発防止に努めていく」といった声明文を発するに留めた方が、人種差別や文化侮辱への対処としては効果的なのではないかと思いました。
色々調べて思ったんですが、白人による黒人への差別にはよく触れられるのに、黒人による犯罪や韓国人による黒人への差別についてはそこまで触れられない気がするのは何故なんでしょうか?
2020/6/1 mtgの相棒のルール変更と禁止制限改訂
2020年6月3日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
相棒のルール変更について
>各ゲーム中に1度だけ、あなたはソーサリーを唱えられるとき(あなたのメイン・フェイズの間でスタックが空であるとき) に(3)を支払うことでサイドボードからあなたの相棒をあなたの手札に加えることができる。これは特別な処理であり、起動型能力ではない。
→サイドからジャイルーダを出すのにのべ9マナ、ヨーリオンを出すのにのべ8マナ必要になってしまいましたが、それでもジャイルーダを使う人はレガシーでも、大会に1人はいそうな気がしました。
(墓堀りの檻に弱いとはいえ、墓地対策が効かず、ベルチャーやスパイと違って十分な枚数の土地も入れられ、ジャイルーダから速攻クリーチャーにつなげればそのまま勝てる可能性があるのは相変わらずなので)
>全体的に、スタンダード、パイオニア、モダンでの相棒を使うデッキの勝率とメタゲームでの割合は高すぎ、そしてレガシーとヴィンテージにおいてはすでに禁止を余儀なくされました。
>我々は各フォーマットの禁止リストにいくつも個別で調整を行うよりも、相棒を使うことによって得られるアドバンテージを全体的に減少させるほうが望ましい答えだと感じました。
→そう感じたんだったら、前回の禁止改定の時にルール変更してくれたら良かったんじゃ?
(前回の禁止改定の時点で、相棒が暴れ回っていたのは分かりきっていたわけですし)
禁止改定について
スタンダード
禁止 裏切りの工作員・創案の火
ヒストリック
一時停止 裏切りの工作員・創案の火
特に気になった点(創案の火)
>ここ数週間に渡って、スタンダードでは《創案の火》デッキが55%の勝率を達成して他の上位10種のアーキタイプに互角または有利な相性を持ち支配的な勝率とメタゲームでの存在感を増してきました。
>我々が将来の環境を作成してテストしてみたところ、《創案の火》はデザインとバランスにとって重大な制限になるカードであることが判明しました。このカードのコストを踏み倒す効果の柔軟性により、《創案の火》デッキは環境に新しい高コスト呪文が加えられるたびに強くなり続けます。
(裏切りの工作員)
>最近《銅纏いののけ者、ルーカ》や《軍団のまとめ役、ウィノータ》で《裏切りの工作員》を直接戦場に出すアーキタイプが増えてきています。
>これらのカードのデザイン意図には強力な高マナ・コストのクリーチャーを展開する創造的な方法を提供することも含まれていますが、これらを使って序盤に《裏切りの工作員》を出すことは相手ににしていて極めて腹立たしく巻き返すのが困難になり得ることが分かりました。
→今更ですが、ここ最近の死者の原野・オーコ・むかしむかし・夏の帳に加え、今回裏切りの工作員・創案の火が禁止になったのを受けて(ウィザーズは、スタンダードのテストプレイすら十分に行っていないのではないか?)と思いました。
ヒストリックは、スタンダードと同じ理由なので省略
5/24に食物連鎖デッキ用にヨーリオンを買いましたが、ルール変更されたのを受けて投入するのを見送ることに決めました。
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034028/
相棒のルール変更について
>各ゲーム中に1度だけ、あなたはソーサリーを唱えられるとき(あなたのメイン・フェイズの間でスタックが空であるとき) に(3)を支払うことでサイドボードからあなたの相棒をあなたの手札に加えることができる。これは特別な処理であり、起動型能力ではない。
→サイドからジャイルーダを出すのにのべ9マナ、ヨーリオンを出すのにのべ8マナ必要になってしまいましたが、それでもジャイルーダを使う人はレガシーでも、大会に1人はいそうな気がしました。
(墓堀りの檻に弱いとはいえ、墓地対策が効かず、ベルチャーやスパイと違って十分な枚数の土地も入れられ、ジャイルーダから速攻クリーチャーにつなげればそのまま勝てる可能性があるのは相変わらずなので)
>全体的に、スタンダード、パイオニア、モダンでの相棒を使うデッキの勝率とメタゲームでの割合は高すぎ、そしてレガシーとヴィンテージにおいてはすでに禁止を余儀なくされました。
>我々は各フォーマットの禁止リストにいくつも個別で調整を行うよりも、相棒を使うことによって得られるアドバンテージを全体的に減少させるほうが望ましい答えだと感じました。
→そう感じたんだったら、前回の禁止改定の時にルール変更してくれたら良かったんじゃ?
(前回の禁止改定の時点で、相棒が暴れ回っていたのは分かりきっていたわけですし)
禁止改定について
スタンダード
禁止 裏切りの工作員・創案の火
ヒストリック
一時停止 裏切りの工作員・創案の火
特に気になった点(創案の火)
>ここ数週間に渡って、スタンダードでは《創案の火》デッキが55%の勝率を達成して他の上位10種のアーキタイプに互角または有利な相性を持ち支配的な勝率とメタゲームでの存在感を増してきました。
>我々が将来の環境を作成してテストしてみたところ、《創案の火》はデザインとバランスにとって重大な制限になるカードであることが判明しました。このカードのコストを踏み倒す効果の柔軟性により、《創案の火》デッキは環境に新しい高コスト呪文が加えられるたびに強くなり続けます。
(裏切りの工作員)
>最近《銅纏いののけ者、ルーカ》や《軍団のまとめ役、ウィノータ》で《裏切りの工作員》を直接戦場に出すアーキタイプが増えてきています。
>これらのカードのデザイン意図には強力な高マナ・コストのクリーチャーを展開する創造的な方法を提供することも含まれていますが、これらを使って序盤に《裏切りの工作員》を出すことは相手ににしていて極めて腹立たしく巻き返すのが困難になり得ることが分かりました。
→今更ですが、ここ最近の死者の原野・オーコ・むかしむかし・夏の帳に加え、今回裏切りの工作員・創案の火が禁止になったのを受けて(ウィザーズは、スタンダードのテストプレイすら十分に行っていないのではないか?)と思いました。
ヒストリックは、スタンダードと同じ理由なので省略
5/24に食物連鎖デッキ用にヨーリオンを買いましたが、ルール変更されたのを受けて投入するのを見送ることに決めました。
2020/5/18 mtgの禁止制限改訂
2020年5月20日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
ブロール
禁止 ドラニスの判事・軍団のまとめ役、ウィノータ
特に気になった点
>1枚のカードで幅広い種類の統率者を完全にシャットダウンできるべきではないという考えがブロールの理念のひとつです。
>我々は《ドラニスの判事》がこの分類に当てはまり、基本的にブロールにおける統率者をデッキの軸にすることによる楽しさと自己表現を損なうと感じたので、これを禁止します。
→相手だけ統率者を唱えられなくするカードは、流石にNGといったところでしょうか。
(統率者戦でも禁止になっても良さそうな気はしますが…)
レガシー
禁止 夢の巣のルールス・黎明起こし、ザーダ
ルールスについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>レガシーの広大なカード・プールの強力な低マナ・コストのパーマネントが《夢の巣のルールス》を相棒として使うことのパワー・レベルとそれのデッキ構築面での制限とを釣り合いの取れないものにしています。
>「デルバー」のバリエーションなど、以前からすでに強力だった複数のアーキタイプは、ルールスを相棒として組み込んでいますが必要となるデッキ構築面での変更が比較的少ないものとなっています。
→Delver系デッキに(宿敵やヴェリアナとは併用できないものの)Willや否定の力を抜くことなく相棒として使えたほか、(睡蓮の花びらやライオンの瞳のダイアモンドでも使い回すために入れるのか?)と思っていたANTや、神ジェイスや3マナのテフェリー・オーコや導師と併用できないにも関わらず奇跡デッキにすら採用されているのを見たら、禁止になるのは当然だと思いました。
ザーダについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>我々は《黎明起こし、ザーダ》を相棒として《厳かなモノリス》を使ったデッキがとても高い勝率を持っていることも見かけました。
>まだ幅広くプレイされてはいませんが、Magic Onlineのメタゲームのデータは、これらのデッキが勝率とメタゲームのシェアの両方において問題を起こすことになると示しています。
→ザーダと厳かなモノリスor玄武岩のモノリスが揃っただけでは勝てないとはいえ、ザーダを相棒として使えるため無限マナを出すだけなら実質1枚コンボになる上に、相性のいい歩行バリスタや創造者カーンも問題なく入れられることを考えたら禁止になっても仕方がないとは思いました。
ルールスはザーダコンボの方を優先していた上に、採用率やDNの記事などを見て(そのうち使えなくなりそうだな…)と思ったため買わなかったからまだ良かったものの、安かったとはいえせっかく4枚揃えたザーダが使う前に禁止になってしまったのは残念でした。
当初はヤバいと言われていたジャイルーダが禁止にならなかったのは、
・相棒の条件として、デッキにWillや渦まく知識といった奇数のカードを入れられず、ジャイルーダの能力を生かすために特化構築にしなければならない
・そのせいか、カラカス・剣鍬&流刑・(サイドからの)赤霊破&紅蓮破・(魂の洞窟や防御の光網がなければ)Willあたりで対処できる上に、それらへの対策も難しい
あたりが原因だと思いました。
ヴィンテージ
禁止 夢の巣のルールス
特に気になった点
>ヴィンテージの広大なカード・プールと強力な制限カードが存在するという性質により、《夢の巣のルールス》の課すデッキ構築面でのコストはこのカードを相棒にすることによって得られる恩恵よりも比較的に制限の緩いものになっています。
>Magic Onlineのリーグでルールスを使用する複数のアーキタイプの勝率は55%を超え、ルールスを使用したデッキ群はメタゲーム内で多すぎる割合を占めており、その流れが収まる兆候は示されていません。
>ヴィンテージにおいてバランス上の理由でカードを制限ではなく禁止が行われるのが稀であることは認識していますが、今回の場合はルールスを制限しても相棒としての使用には影響がないという珍しい事例であるため、それを主な理由として禁止という変更を行いました。
→相棒のシステム上、制限にしても意味がないとはいえ、まさか(パワー9すら制限止まりの)ヴィンテージから禁止カードが出るとは思いませんでした。
ルールスがレガシーどころか、ヴィンテージですら禁止になったのを見て(そのうちモダンでも禁止になるな…)と思いました。
(ヴァラクートやトロンといった土地コンボには入らず、神ジェイス・血編み・ヴェリアナあたりとは併用できないとはいえ、採用率が高く、ミシュラのガラクタを1回唱えただけで除去されたとしてもアドバンテージを2つ稼げることを考えたら禁止になってもおかしくないはず)
今回のレガシー・ヴィンテージの禁止改定で禁止になったのがいずれも相棒だということを考えたら、
・今回の禁止改定では、レガシーではルールスとザーダ、ヴィンテージではルールスの相棒指定のみ禁止
・相棒を公開した場合は、手札を1枚下に送るようにルール変更
これらさえ行えば、相棒だらけになることは防げそうな気はしました。
(とはいえ、これらを行ったらルールスやザーダの採用率は大幅に落ちそうですが)
Delver系デッキや奇跡デッキにウルザorミシュラのガラクタを入れるという発想ができなかったため、ルールスが入るとは思わなかったのが完全に誤算でしたね…
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034000/
ブロール
禁止 ドラニスの判事・軍団のまとめ役、ウィノータ
特に気になった点
>1枚のカードで幅広い種類の統率者を完全にシャットダウンできるべきではないという考えがブロールの理念のひとつです。
>我々は《ドラニスの判事》がこの分類に当てはまり、基本的にブロールにおける統率者をデッキの軸にすることによる楽しさと自己表現を損なうと感じたので、これを禁止します。
→相手だけ統率者を唱えられなくするカードは、流石にNGといったところでしょうか。
(統率者戦でも禁止になっても良さそうな気はしますが…)
レガシー
禁止 夢の巣のルールス・黎明起こし、ザーダ
ルールスについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>レガシーの広大なカード・プールの強力な低マナ・コストのパーマネントが《夢の巣のルールス》を相棒として使うことのパワー・レベルとそれのデッキ構築面での制限とを釣り合いの取れないものにしています。
>「デルバー」のバリエーションなど、以前からすでに強力だった複数のアーキタイプは、ルールスを相棒として組み込んでいますが必要となるデッキ構築面での変更が比較的少ないものとなっています。
→Delver系デッキに(宿敵やヴェリアナとは併用できないものの)Willや否定の力を抜くことなく相棒として使えたほか、(睡蓮の花びらやライオンの瞳のダイアモンドでも使い回すために入れるのか?)と思っていたANTや、神ジェイスや3マナのテフェリー・オーコや導師と併用できないにも関わらず奇跡デッキにすら採用されているのを見たら、禁止になるのは当然だと思いました。
ザーダについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>我々は《黎明起こし、ザーダ》を相棒として《厳かなモノリス》を使ったデッキがとても高い勝率を持っていることも見かけました。
>まだ幅広くプレイされてはいませんが、Magic Onlineのメタゲームのデータは、これらのデッキが勝率とメタゲームのシェアの両方において問題を起こすことになると示しています。
→ザーダと厳かなモノリスor玄武岩のモノリスが揃っただけでは勝てないとはいえ、ザーダを相棒として使えるため無限マナを出すだけなら実質1枚コンボになる上に、相性のいい歩行バリスタや創造者カーンも問題なく入れられることを考えたら禁止になっても仕方がないとは思いました。
ルールスはザーダコンボの方を優先していた上に、採用率やDNの記事などを見て(そのうち使えなくなりそうだな…)と思ったため買わなかったからまだ良かったものの、安かったとはいえせっかく4枚揃えたザーダが使う前に禁止になってしまったのは残念でした。
当初はヤバいと言われていたジャイルーダが禁止にならなかったのは、
・相棒の条件として、デッキにWillや渦まく知識といった奇数のカードを入れられず、ジャイルーダの能力を生かすために特化構築にしなければならない
・そのせいか、カラカス・剣鍬&流刑・(サイドからの)赤霊破&紅蓮破・(魂の洞窟や防御の光網がなければ)Willあたりで対処できる上に、それらへの対策も難しい
あたりが原因だと思いました。
ヴィンテージ
禁止 夢の巣のルールス
特に気になった点
>ヴィンテージの広大なカード・プールと強力な制限カードが存在するという性質により、《夢の巣のルールス》の課すデッキ構築面でのコストはこのカードを相棒にすることによって得られる恩恵よりも比較的に制限の緩いものになっています。
>Magic Onlineのリーグでルールスを使用する複数のアーキタイプの勝率は55%を超え、ルールスを使用したデッキ群はメタゲーム内で多すぎる割合を占めており、その流れが収まる兆候は示されていません。
>ヴィンテージにおいてバランス上の理由でカードを制限ではなく禁止が行われるのが稀であることは認識していますが、今回の場合はルールスを制限しても相棒としての使用には影響がないという珍しい事例であるため、それを主な理由として禁止という変更を行いました。
→相棒のシステム上、制限にしても意味がないとはいえ、まさか(パワー9すら制限止まりの)ヴィンテージから禁止カードが出るとは思いませんでした。
ルールスがレガシーどころか、ヴィンテージですら禁止になったのを見て(そのうちモダンでも禁止になるな…)と思いました。
(ヴァラクートやトロンといった土地コンボには入らず、神ジェイス・血編み・ヴェリアナあたりとは併用できないとはいえ、採用率が高く、ミシュラのガラクタを1回唱えただけで除去されたとしてもアドバンテージを2つ稼げることを考えたら禁止になってもおかしくないはず)
今回のレガシー・ヴィンテージの禁止改定で禁止になったのがいずれも相棒だということを考えたら、
・今回の禁止改定では、レガシーではルールスとザーダ、ヴィンテージではルールスの相棒指定のみ禁止
・相棒を公開した場合は、手札を1枚下に送るようにルール変更
これらさえ行えば、相棒だらけになることは防げそうな気はしました。
(とはいえ、これらを行ったらルールスやザーダの採用率は大幅に落ちそうですが)
Delver系デッキや奇跡デッキにウルザorミシュラのガラクタを入れるという発想ができなかったため、ルールスが入るとは思わなかったのが完全に誤算でしたね…
2020/3/9 mtgの禁止制限改訂
2020年3月11日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
モダン
禁止 むかしむかし
むかしむかしについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>《むかしむかし》のもたらす安定性はメタゲーム内の他のデッキと比較してはるかに安定した序盤のゲームプランの成立を可能とし、ゲームプレイの進行の多様性を損なう結果になりました。
>将来的に、《むかしむかし》はクリーチャーや土地に基づいたコンボを簡単に揃えることができてしまうというデザイン上の制約を引き起こします。
→初手にあればもちろんのこと、2マナで撃ってもクリーチャー・土地コンボ系のデッキを安定させるには十分すぎたことを考えたら、(思案・定業が禁止のモダンでは)禁止になっても仕方がない気がしました。
(0マナで撃てなくても「クリーチャー・土地限定の衝動みたいなカード」と見れば十分強い気がしてきました。火想者の予見ありきとはいえ、衝動はレガシーの全知デッキにも入るぐらいですし)
毎回言ってる気がしますが、初手に来なければ0マナで撃てる確率が下がるためか、全く評価してなかった私の見る目のなさを痛感しました。
レガシー
禁止 死の国からの脱出
死の国からの脱出について書かれた記事の中で、特に気になった点
>『テーロス還魂記』の発売以降、我々は《死の国からの脱出》、《ライオンの瞳のダイアモンド》《思考停止》の相互作用を中心としたデッキの組み合わせの進化を監視してきました。
>しかしこれらのデッキが洗練されるにつれて、《死の国からの脱出》の《ライオンの瞳のダイアモンド》と《思考停止》との相互作用が今後のレガシーに問題を残すことが勝率の上昇によって明らかになってきました。
→ANTと違ってWillを4枚採用でき、コンボパーツの思考停止がフィニッシャーにもなり、コンボさえ決まればぶどう弾やタッサの神託者で夏の帳を無視して勝てるのは強いと思います。
しかし、ライオンの瞳のダイアモンド・思考停止は墓地にあってもいいとはいえ3枚コンボである上に、墓地対策に引っかかるのもあって禁止になるとまでは思ってなかったため(実際、1ヶ月前にそう言った)、禁止になったのを知って驚きました。
(これが禁止になるなら、納墓からの再活性・死体発掘・動く死体・御霊の復讐・浅すぎる墓穴でグリセルを釣ったり、墓地を経由しない実物提示教育→全知→エムラはいいのか?と思ったぐらいですし)
モダンでむかしむかしが禁止になったのを受けて(そのうち、古きものの活性も禁止になるんじゃないか?)と思いました。
と同時に、レガシーでむかしむかしを使うなら、今が絶好の買い時だとも思いました。(レガシーでは禁止にならなさそうですし)
とはいえ、オーコはレガシーで禁止になってもおかしくない気はしたので、買うとしたらどうしても使いたくなったか、エルドレインの王権がスタン落ちした時に禁止でなかったら2~3枚買う予定です。
(あと、コンボデッキとの相性が良すぎる夏の帳もヤバいかも)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0033869/
モダン
禁止 むかしむかし
むかしむかしについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>《むかしむかし》のもたらす安定性はメタゲーム内の他のデッキと比較してはるかに安定した序盤のゲームプランの成立を可能とし、ゲームプレイの進行の多様性を損なう結果になりました。
>将来的に、《むかしむかし》はクリーチャーや土地に基づいたコンボを簡単に揃えることができてしまうというデザイン上の制約を引き起こします。
→初手にあればもちろんのこと、2マナで撃ってもクリーチャー・土地コンボ系のデッキを安定させるには十分すぎたことを考えたら、(思案・定業が禁止のモダンでは)禁止になっても仕方がない気がしました。
(0マナで撃てなくても「クリーチャー・土地限定の衝動みたいなカード」と見れば十分強い気がしてきました。火想者の予見ありきとはいえ、衝動はレガシーの全知デッキにも入るぐらいですし)
毎回言ってる気がしますが、初手に来なければ0マナで撃てる確率が下がるためか、全く評価してなかった私の見る目のなさを痛感しました。
レガシー
禁止 死の国からの脱出
死の国からの脱出について書かれた記事の中で、特に気になった点
>『テーロス還魂記』の発売以降、我々は《死の国からの脱出》、《ライオンの瞳のダイアモンド》《思考停止》の相互作用を中心としたデッキの組み合わせの進化を監視してきました。
>しかしこれらのデッキが洗練されるにつれて、《死の国からの脱出》の《ライオンの瞳のダイアモンド》と《思考停止》との相互作用が今後のレガシーに問題を残すことが勝率の上昇によって明らかになってきました。
→ANTと違ってWillを4枚採用でき、コンボパーツの思考停止がフィニッシャーにもなり、コンボさえ決まればぶどう弾やタッサの神託者で夏の帳を無視して勝てるのは強いと思います。
しかし、ライオンの瞳のダイアモンド・思考停止は墓地にあってもいいとはいえ3枚コンボである上に、墓地対策に引っかかるのもあって禁止になるとまでは思ってなかったため(実際、1ヶ月前にそう言った)、禁止になったのを知って驚きました。
(これが禁止になるなら、納墓からの再活性・死体発掘・動く死体・御霊の復讐・浅すぎる墓穴でグリセルを釣ったり、墓地を経由しない実物提示教育→全知→エムラはいいのか?と思ったぐらいですし)
モダンでむかしむかしが禁止になったのを受けて(そのうち、古きものの活性も禁止になるんじゃないか?)と思いました。
と同時に、レガシーでむかしむかしを使うなら、今が絶好の買い時だとも思いました。(レガシーでは禁止にならなさそうですし)
とはいえ、オーコはレガシーで禁止になってもおかしくない気はしたので、買うとしたらどうしても使いたくなったか、エルドレインの王権がスタン落ちした時に禁止でなかったら2~3枚買う予定です。
(あと、コンボデッキとの相性が良すぎる夏の帳もヤバいかも)
2020/1/13 mtgの禁止制限改訂
2020年1月15日 mtg-禁止改訂 コメント (2)詳しくはこちら
モダン
禁止 王冠泥棒、オーコ・オパールのモックス・マイコシンスの格子
モダン環境について書かれた記事の中で、特に気になった点
>ここ数週間にわたり、《最高工匠卿、ウルザ》を使った青緑ベースのデッキが競技モダンの上位層に増加していて、Magic Onlineのリーグで最も多く5-0を達成し、ミラーマッチ以外での勝率は55%以上を維持していました。またこのデッキは他の主要な10の競技的なデッキのうち9つに対して有利であり、メタゲームが自力で調整不可能であることを示したいます。
オーコについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>《王冠泥棒、オーコ》はリーグやテーブルトップのトーナメントのデッキの40%近くで使われていて、競技モダンで最も使われているカードになりました。
>ゲームプレイの健全性の改善と、ウルザ・デッキや他のデッキを弱体化させるため《王冠泥棒、オーコ》はモダンで禁止されます。
→オーコを刷ったウィザーズの開発陣と、強さを見抜けなかった私の話は既にスタンダードの際にしたので、これからは「どうかレガシーでも禁止になりますように…」と思うことにしました。
(正直、オーコがいるというだけでマーベリックを使う気がしなくなったので。ついでに、コンボデッキにすら当然のように入る夏の帳も禁止にしてほしいです)
オパールのモックスについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>ゲーム序盤の高速マナ供給源として《オパールのモックス》は爆発的な攻撃や1ターンで勝利するコンボ、もしくはプリズン要素で相手をロックするなどの素早く突然にゲームを決めてしまう戦略に長い間貢献してきました。
>現在のウルザ・デッキの最も強い前提カードであり、過去に懸念され将来バランス上の問題を引き起こす可能性が高いカード~
→親和も巻き添えを喰らってしまう点が気になりますが、他に軽いアーティファクトを2つ出すだけでレガシーですら禁止のMoxenのように使える上に、金属モックスが禁止なことを考えたら仕方がないと思いました。
マイコシンスの格子について書かれた記事の中で、特に気になった点
(一部書き換えあり)
>エルドラージ・トロンやその他のトロン・デッキでよく使われている《大いなる創造者、カーン》と《マイコシンスの格子》の組み合わせは、対戦相手がこれ以上呪文を唱えることを完全に封じてしまいます。この組み合わせを搭載したデッキは概ね他の勝ち手段を持っていますが、この組み合わせを搭載するために生じるデッキ構築上の制約は小さく、競技プレイにおいて楽しいと感じる限度よりも頻繁に使われています。
→だったら単体では弱い上に対処しやすいマイコシンスの格子じゃなくて、対処しにくい上に単体でも強いカーンの方を禁止にすべきでは?
オーコはそのうちレガシーでも使えなくなると思うので、欲しくなっても当分の間は買わないことに決めました。
(一応青の打ち消しはもちろんのこと、紅蓮破・赤霊破でも弾け、針で止められる上に、ANT・全知デッキ相手には効果が薄いものの、その理屈でいけばレンと六番は禁止にならなかったはずなので…)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0033630/
モダン
禁止 王冠泥棒、オーコ・オパールのモックス・マイコシンスの格子
モダン環境について書かれた記事の中で、特に気になった点
>ここ数週間にわたり、《最高工匠卿、ウルザ》を使った青緑ベースのデッキが競技モダンの上位層に増加していて、Magic Onlineのリーグで最も多く5-0を達成し、ミラーマッチ以外での勝率は55%以上を維持していました。またこのデッキは他の主要な10の競技的なデッキのうち9つに対して有利であり、メタゲームが自力で調整不可能であることを示したいます。
オーコについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>《王冠泥棒、オーコ》はリーグやテーブルトップのトーナメントのデッキの40%近くで使われていて、競技モダンで最も使われているカードになりました。
>ゲームプレイの健全性の改善と、ウルザ・デッキや他のデッキを弱体化させるため《王冠泥棒、オーコ》はモダンで禁止されます。
→オーコを刷ったウィザーズの開発陣と、強さを見抜けなかった私の話は既にスタンダードの際にしたので、これからは「どうかレガシーでも禁止になりますように…」と思うことにしました。
(正直、オーコがいるというだけでマーベリックを使う気がしなくなったので。ついでに、コンボデッキにすら当然のように入る夏の帳も禁止にしてほしいです)
オパールのモックスについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>ゲーム序盤の高速マナ供給源として《オパールのモックス》は爆発的な攻撃や1ターンで勝利するコンボ、もしくはプリズン要素で相手をロックするなどの素早く突然にゲームを決めてしまう戦略に長い間貢献してきました。
>現在のウルザ・デッキの最も強い前提カードであり、過去に懸念され将来バランス上の問題を引き起こす可能性が高いカード~
→親和も巻き添えを喰らってしまう点が気になりますが、他に軽いアーティファクトを2つ出すだけでレガシーですら禁止のMoxenのように使える上に、金属モックスが禁止なことを考えたら仕方がないと思いました。
マイコシンスの格子について書かれた記事の中で、特に気になった点
(一部書き換えあり)
>エルドラージ・トロンやその他のトロン・デッキでよく使われている《大いなる創造者、カーン》と《マイコシンスの格子》の組み合わせは、対戦相手がこれ以上呪文を唱えることを完全に封じてしまいます。この組み合わせを搭載したデッキは概ね他の勝ち手段を持っていますが、この組み合わせを搭載するために生じるデッキ構築上の制約は小さく、競技プレイにおいて楽しいと感じる限度よりも頻繁に使われています。
→だったら単体では弱い上に対処しやすいマイコシンスの格子じゃなくて、対処しにくい上に単体でも強いカーンの方を禁止にすべきでは?
オーコはそのうちレガシーでも使えなくなると思うので、欲しくなっても当分の間は買わないことに決めました。
(一応青の打ち消しはもちろんのこと、紅蓮破・赤霊破でも弾け、針で止められる上に、ANT・全知デッキ相手には効果が薄いものの、その理屈でいけばレンと六番は禁止にならなかったはずなので…)
2019/11/18 mtgの禁止制限改訂
2019年11月19日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
スタンダード
禁止 王冠泥棒、オーコ・むかしむかし・夏の帳
オーコについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>《王冠泥棒、オーコ》はデッキの軸となるクリーチャーやアーティファクトを締め出すことによってメタゲームとスタンダードのゲームプレイの多様性を減少させています。
→既にナーセットやテフェリー、内にいる獣があるのもあって、モダン以下でオーコを全く評価してなかった私が言うのもなんですが、グリセル・エムラといった大型クリーチャーのみならず、虚空の杯・三なる宝球・罠の橋・各種装備品といった厄介なアーティファクトをも「+1能力で」「永続的に」ただの3/3に変えてしまう「3マナの」プレインズウォーカーを刷ってしまったウィザーズの開発陣(と、初見でオーコを全く評価しなかった私)は本当にどうかしてると思いました。
→オーコ「テフェリーやナーセットは高く評価していた癖に、なんで俺は全く評価しなかったんだ?」
(オーコのただの3/3に変える能力が-3能力だったら、スタンでも禁止されなかったとは思いますが、そうなったらモダン以下ではサイドに入るかどうかといったところになりそうです)
むかしむかしと夏の帳については、スタンダードをやってない上に、オーコの巻き添えを食って禁止になった気がしたのでノーコメントで
(なお、オーコはブロールでも禁止になった模様)
レガシー
禁止 レンと六番
レンと六番について書かれた記事の中で、特に気になった点
>最も重要なのは、このデッキ(レンと六番入りティムール・デルバー)は他の最も多くプレイされている10のデッキに対して、すべて有利であるということです。
>《レンと六番》は普通に強いカードですが、レガシーにおいては《不毛の大地》との相互作用と、《ルーンの母》、《スレイベンの守護者、サリア》、《若き紅蓮術士》などの伝統的に人気のある環境を定義するタフネス1のクリーチャーとのやり取りにより特に強力です。
→オーコと違い、こちらは初見の時点で「+1能力でフェッチランドや不毛などを回収してアドバンテージを稼ぎ、-1能力でタフネス1のクリーチャーを焼ける」点は評価してましたが、ティムール・デルバーをトップメタに押し上げることまでは予想できませんでした。
(他にも、4色コントロールに入っていたのが確認できました。そういえば、ティムール・デルバーにも宝船の巡航が採用されてましたよね…)
ヴィンテージ
制限 覆いを割く者、ナーセット
→Ancestral Recall・ギタ調・Bazaar of Baghdadといった、ドローソースを相手だけ止めてしまうのが制限になった理由だそうです。
(渦まく知識・思案が4枚使えるレガシーで禁止にならず、ヴィンテージで制限になったのは、ヴィンテージはクリーチャーが少なめなのが理由だとどこかに書かれていました)
オーコがスタンダードで禁止になったのは、実際にプレイしていない私でも当然だとしか思えませんでしたが、レガシーでレンと六番が禁止になったのは少し驚きました。
(特殊土地やタフネス1のクリーチャーに頼らないデッキを使えばいいと思っていたので。おそらく「2マナの」プレインズウォーカーだから禁止になったのでしょう)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0033448/
スタンダード
禁止 王冠泥棒、オーコ・むかしむかし・夏の帳
オーコについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>《王冠泥棒、オーコ》はデッキの軸となるクリーチャーやアーティファクトを締め出すことによってメタゲームとスタンダードのゲームプレイの多様性を減少させています。
→既にナーセットやテフェリー、内にいる獣があるのもあって、モダン以下でオーコを全く評価してなかった私が言うのもなんですが、グリセル・エムラといった大型クリーチャーのみならず、虚空の杯・三なる宝球・罠の橋・各種装備品といった厄介なアーティファクトをも「+1能力で」「永続的に」ただの3/3に変えてしまう「3マナの」プレインズウォーカーを刷ってしまったウィザーズの開発陣(と、初見でオーコを全く評価しなかった私)は本当にどうかしてると思いました。
→オーコ「テフェリーやナーセットは高く評価していた癖に、なんで俺は全く評価しなかったんだ?」
(オーコのただの3/3に変える能力が-3能力だったら、スタンでも禁止されなかったとは思いますが、そうなったらモダン以下ではサイドに入るかどうかといったところになりそうです)
むかしむかしと夏の帳については、スタンダードをやってない上に、オーコの巻き添えを食って禁止になった気がしたのでノーコメントで
(なお、オーコはブロールでも禁止になった模様)
レガシー
禁止 レンと六番
レンと六番について書かれた記事の中で、特に気になった点
>最も重要なのは、このデッキ(レンと六番入りティムール・デルバー)は他の最も多くプレイされている10のデッキに対して、すべて有利であるということです。
>《レンと六番》は普通に強いカードですが、レガシーにおいては《不毛の大地》との相互作用と、《ルーンの母》、《スレイベンの守護者、サリア》、《若き紅蓮術士》などの伝統的に人気のある環境を定義するタフネス1のクリーチャーとのやり取りにより特に強力です。
→オーコと違い、こちらは初見の時点で「+1能力でフェッチランドや不毛などを回収してアドバンテージを稼ぎ、-1能力でタフネス1のクリーチャーを焼ける」点は評価してましたが、ティムール・デルバーをトップメタに押し上げることまでは予想できませんでした。
(他にも、4色コントロールに入っていたのが確認できました。そういえば、ティムール・デルバーにも宝船の巡航が採用されてましたよね…)
ヴィンテージ
制限 覆いを割く者、ナーセット
→Ancestral Recall・ギタ調・Bazaar of Baghdadといった、ドローソースを相手だけ止めてしまうのが制限になった理由だそうです。
(渦まく知識・思案が4枚使えるレガシーで禁止にならず、ヴィンテージで制限になったのは、ヴィンテージはクリーチャーが少なめなのが理由だとどこかに書かれていました)
オーコがスタンダードで禁止になったのは、実際にプレイしていない私でも当然だとしか思えませんでしたが、レガシーでレンと六番が禁止になったのは少し驚きました。
(特殊土地やタフネス1のクリーチャーに頼らないデッキを使えばいいと思っていたので。おそらく「2マナの」プレインズウォーカーだから禁止になったのでしょう)
2019/10/21 mtgの禁止制限改訂と新フォーマット「パイオニア」
2019年10月22日 mtg-禁止改訂mtgの禁止制限改訂の詳細はこちら
スタンダード
禁止 死者の原野
(スタンダードには興味がないので、この件に関してはノーコメントで。ただ、次の禁止改定でオーコが禁止になりそうな予感はしました)
パウパー
禁止 アーカムの天測儀
これについての記事を見てみたら、「3色以上の雪崩しを使うデッキのマナ基盤をアドバンテージを得ながら1マナで安定させられる上に、コーの空漁師などとのシナジーが強すぎるから禁止にした(意訳)」といった感じの事が書かれていました。
(実際に勝率も高かったそうです)
新フォーマット「パイオニア」の詳細はこちら
使えるセット:『ラヴニカへの回帰』以降のセット
禁止カード:溢れかえる岸辺、汚染された三角州、血染めのぬかるみ、樹木茂る山麓、吹きさらしの荒野
→フェッチランドが禁止されているので、レガシーですら禁止された死儀礼・宝船の巡航・時を越えた探索が禁止にならなさそうなのはいいと思いましたが、一方でクリーチャーやプレインズウォーカーが強くそれらへの対処カードが弱いフォーマットにも思えてきたので、実際に運営されだしたら集合した中隊は禁止になりそうな気がしました。
(クリーチャー主体の環境が好きな人にはおすすめできるかも)
特に気になった点
>モダンで使用できる最古のセットが発売されたのは、2003年――16年前のことです。今やカードプールはかなり広くなり、「ローテーション後もスタンダードから去ったカードを使えるフォーマット」としての役割は担えなくなっているのです。そこで、ローテーション後もスタンダードから去ったカードを使いたいと願う比較的最近始めたプレイヤーのために、かつてモダンが担っていた役割をパイオニアが担い、スタンダードとの架け橋となります。
→近い将来、パイオニアも「ローテーション後もスタンダードから去ったカードを使えるフォーマット」としての役割は担えなくなるのは間違いないでしょう。
(一部では、エクステンデッドの復活を望む声も上がっていました)
モダンでホガークの巻き添えを喰らって禁止になったと思われる、信仰無き物あさりは結局解禁されませんでしたね…
(墓地利用系のデッキを大幅に強化するカードとはいえ、墓地対策カードも質・量ともに豊富に存在するのだから解禁されても良さそうな気はするんですが…)
パイオニアに参入するかは、今後の動向を見てから決める予定です。
(ひょっとしたら、すぐに廃れるかもしれませんし)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0033235/
スタンダード
禁止 死者の原野
(スタンダードには興味がないので、この件に関してはノーコメントで。ただ、次の禁止改定でオーコが禁止になりそうな予感はしました)
パウパー
禁止 アーカムの天測儀
これについての記事を見てみたら、「3色以上の雪崩しを使うデッキのマナ基盤をアドバンテージを得ながら1マナで安定させられる上に、コーの空漁師などとのシナジーが強すぎるから禁止にした(意訳)」といった感じの事が書かれていました。
(実際に勝率も高かったそうです)
新フォーマット「パイオニア」の詳細はこちら
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0033236/
使えるセット:『ラヴニカへの回帰』以降のセット
禁止カード:溢れかえる岸辺、汚染された三角州、血染めのぬかるみ、樹木茂る山麓、吹きさらしの荒野
→フェッチランドが禁止されているので、レガシーですら禁止された死儀礼・宝船の巡航・時を越えた探索が禁止にならなさそうなのはいいと思いましたが、一方でクリーチャーやプレインズウォーカーが強くそれらへの対処カードが弱いフォーマットにも思えてきたので、実際に運営されだしたら集合した中隊は禁止になりそうな気がしました。
(クリーチャー主体の環境が好きな人にはおすすめできるかも)
特に気になった点
>モダンで使用できる最古のセットが発売されたのは、2003年――16年前のことです。今やカードプールはかなり広くなり、「ローテーション後もスタンダードから去ったカードを使えるフォーマット」としての役割は担えなくなっているのです。そこで、ローテーション後もスタンダードから去ったカードを使いたいと願う比較的最近始めたプレイヤーのために、かつてモダンが担っていた役割をパイオニアが担い、スタンダードとの架け橋となります。
→近い将来、パイオニアも「ローテーション後もスタンダードから去ったカードを使えるフォーマット」としての役割は担えなくなるのは間違いないでしょう。
(一部では、エクステンデッドの復活を望む声も上がっていました)
モダンでホガークの巻き添えを喰らって禁止になったと思われる、信仰無き物あさりは結局解禁されませんでしたね…
(墓地利用系のデッキを大幅に強化するカードとはいえ、墓地対策カードも質・量ともに豊富に存在するのだから解禁されても良さそうな気はするんですが…)
パイオニアに参入するかは、今後の動向を見てから決める予定です。
(ひょっとしたら、すぐに廃れるかもしれませんし)
2019/8/26 mtgの禁止制限改訂
2019年8月28日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
スタンダード
解禁 暴れ回るフェロキドン
(スタンダードには興味がないので、この件に関してはノーコメントで)
モダン
禁止 甦る死滅都市、ホガーク、信仰無き物あさり
ホガークについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>大量の墓地対策がメインデッキに入れられた後もホガーク・デッキは高い勝率を誇示したというメタゲームが自己修正不能である兆候が見られたため、我々はこのデッキを弱体化するために《黄泉からの橋》を禁止しました。
>去年1年間、墓地を基盤とした戦略はモダンのメタゲームの大きな部分を占めていて、デッキ構築の多様性を抑圧していました。これは《外科的摘出》、《虚空の力線》、《安らかなる眠り》といった墓地対策カードの強引なメインデッキ投入となって跳ね返ってきました。
→(一部で安らかなる眠りですら遅いと言われる上に、サイド後は活性の力や暗殺者の戦利品などが増量されるためか)メインから墓地対策されたにも関わらず高い勝率を誇った「ホガーク・ヴァイン」のキーパーツであるホガークが禁止になるのは当然だと思いました。
(ホガークの強さに気付かなかった私が言うのもなんですが、ウィザーズはホガークの調整を真面目に行ったのか?と疑いたくなりました。もしホガークが墓地から唱えられなければ禁止にはならなかったでしょうが、その場合はモダンでは使われなかったかも)
(おまけ)もしレガシーでメインから外科的や虚空の力戦が入り始めたら、赤黒リアニやドレッジで高い勝率を誇るのはまず不可能だと思われるので、モダン環境を知らなくても「ホガーク・ヴァイン」は異常としか思えなくなると思います。
信仰無き物あさりについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>Magic Onlineとテーブルトップのトーナメントから収集したデータでは、ここ1年の間で最も勝っているモダンのデッキは、どの時点を切り取ってみても基本的に《信仰無き物あさり》デッキです。これには「ホロウワン」、「イゼット・フェニックス」、「ドレッジ」と「ブリッジ・ヴァイン」のバリエーションが(ホガークの登場の前も後も)含まれます。墓地、カードを捨てること、軽い呪文を唱えることに相互作用を持った新しいカードデザインが発売されるにつれて、効果的に手札と墓地を整える《信仰無き物あさり》の強さは増大し続けてきました。
→個人的には物あさりが禁止になるとは思ってなかったので、禁止になると聞いて驚きました。
(物あさりはホガークの巻き添えで禁止になったとしか思えないので、次の禁止改定で解禁されてもおかしくはないと思っています)
解禁 石鍛冶の神秘家
石鍛冶について書かれた記事の中で、特に気になった点
>《石鍛冶の神秘家》の危険性、そして今まで禁止リストに残っていた理由とは、戦場に向かってプレイする素直なデッキの戦略に対して最も強いからです。我々はないと考えていますが、《石鍛冶の神秘家》がこのタイプのゲームプレイを抑圧する状況も考えられ、その場合は(モダンでの《ゴルガリの墓トロール》の歴史のように)《石鍛冶の神秘家》の妥当性を再検討します。
→殴打頭蓋があるとはいえ、十手は禁止されている上にコンボデッキ相手には少し遅く、フェアデッキでもサイドからはアーティファクト対策はするはずなので、石鍛冶が解禁されてもモダン環境を抑圧することはないでしょう。
(ただ、ウルザソプターで弱者の剣もサーチできるクリーチャーとして入る点には注意した方が良さそうですが。あと石鍛冶の価格が1万を超えててびっくりしました)
ヴィンテージ
制限 大いなる創造者、カーン、神秘の炉、精神的つまづき、ゴルガリの墓トロール
制限解除 Fastbond
→ヴィンテージについてもよく知らないので、コメントはしない方向でいきたいです。
(これで精神的つまづきを4枚使えるフォーマットはなくなったってことでいいんでしょうか?)
モダンでホガークが禁止になったのを受けてホガークが安くなるはずなので、レガシー用にホガークを4枚揃えたいところです。
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0032973/
スタンダード
解禁 暴れ回るフェロキドン
(スタンダードには興味がないので、この件に関してはノーコメントで)
モダン
禁止 甦る死滅都市、ホガーク、信仰無き物あさり
ホガークについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>大量の墓地対策がメインデッキに入れられた後もホガーク・デッキは高い勝率を誇示したというメタゲームが自己修正不能である兆候が見られたため、我々はこのデッキを弱体化するために《黄泉からの橋》を禁止しました。
>去年1年間、墓地を基盤とした戦略はモダンのメタゲームの大きな部分を占めていて、デッキ構築の多様性を抑圧していました。これは《外科的摘出》、《虚空の力線》、《安らかなる眠り》といった墓地対策カードの強引なメインデッキ投入となって跳ね返ってきました。
→(一部で安らかなる眠りですら遅いと言われる上に、サイド後は活性の力や暗殺者の戦利品などが増量されるためか)メインから墓地対策されたにも関わらず高い勝率を誇った「ホガーク・ヴァイン」のキーパーツであるホガークが禁止になるのは当然だと思いました。
(ホガークの強さに気付かなかった私が言うのもなんですが、ウィザーズはホガークの調整を真面目に行ったのか?と疑いたくなりました。もしホガークが墓地から唱えられなければ禁止にはならなかったでしょうが、その場合はモダンでは使われなかったかも)
(おまけ)もしレガシーでメインから外科的や虚空の力戦が入り始めたら、赤黒リアニやドレッジで高い勝率を誇るのはまず不可能だと思われるので、モダン環境を知らなくても「ホガーク・ヴァイン」は異常としか思えなくなると思います。
信仰無き物あさりについて書かれた記事の中で、特に気になった点
>Magic Onlineとテーブルトップのトーナメントから収集したデータでは、ここ1年の間で最も勝っているモダンのデッキは、どの時点を切り取ってみても基本的に《信仰無き物あさり》デッキです。これには「ホロウワン」、「イゼット・フェニックス」、「ドレッジ」と「ブリッジ・ヴァイン」のバリエーションが(ホガークの登場の前も後も)含まれます。墓地、カードを捨てること、軽い呪文を唱えることに相互作用を持った新しいカードデザインが発売されるにつれて、効果的に手札と墓地を整える《信仰無き物あさり》の強さは増大し続けてきました。
→個人的には物あさりが禁止になるとは思ってなかったので、禁止になると聞いて驚きました。
(物あさりはホガークの巻き添えで禁止になったとしか思えないので、次の禁止改定で解禁されてもおかしくはないと思っています)
解禁 石鍛冶の神秘家
石鍛冶について書かれた記事の中で、特に気になった点
>《石鍛冶の神秘家》の危険性、そして今まで禁止リストに残っていた理由とは、戦場に向かってプレイする素直なデッキの戦略に対して最も強いからです。我々はないと考えていますが、《石鍛冶の神秘家》がこのタイプのゲームプレイを抑圧する状況も考えられ、その場合は(モダンでの《ゴルガリの墓トロール》の歴史のように)《石鍛冶の神秘家》の妥当性を再検討します。
→殴打頭蓋があるとはいえ、十手は禁止されている上にコンボデッキ相手には少し遅く、フェアデッキでもサイドからはアーティファクト対策はするはずなので、石鍛冶が解禁されてもモダン環境を抑圧することはないでしょう。
(ただ、ウルザソプターで弱者の剣もサーチできるクリーチャーとして入る点には注意した方が良さそうですが。あと石鍛冶の価格が1万を超えててびっくりしました)
ヴィンテージ
制限 大いなる創造者、カーン、神秘の炉、精神的つまづき、ゴルガリの墓トロール
制限解除 Fastbond
→ヴィンテージについてもよく知らないので、コメントはしない方向でいきたいです。
(これで精神的つまづきを4枚使えるフォーマットはなくなったってことでいいんでしょうか?)
モダンでホガークが禁止になったのを受けてホガークが安くなるはずなので、レガシー用にホガークを4枚揃えたいところです。
2019/7/8 mtgの禁止制限改訂
2019年7月10日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0032686/
モダン
禁止 黄泉からの橋
引用元の記事のホガークヴァインについて書かれた部分を見て、気になった点
>我々は、このデッキを弱体化しつつ残りのメタゲームへの影響を最小限にする、いくつかの禁止カードの可能性について議論をしました。《甦る死滅都市、ホガーク》、《狂気の祭壇》、《黄泉からの橋》です。いずれの選択肢も可能ですが、我々は《黄泉からの橋》が将来再びメタゲームの不均衡を起こす可能性が最も高いカードだと認識しました。
→ホガークが禁止にならなかったのは商売事情もありそうですが、黄泉からの橋から出るゾンビさえいなければホガークが出しづらくなるから問題ないと思われたからでしょうか?
(ここで信仰無き物あさりが禁止にならなかったのを受けて、これ以降も禁止になることはないだろうとほぼ確信しました)
ここでもモダンでアロサウルス乗りが禁止にならなかったのは、手札破壊や打ち消し(個人的にはアロサウルス乗りに差し戻しを撃ちたいところ)、人間デッキの翻弄する魔道士(指定はアロサウルス乗り)に弱い点よりも、(墓地対策の影響を受けず、召喚士の契約があるとはいえ)コンボを決めるためにアロサウルス乗り+新生化or異界の進化+他の緑のカード×2の4枚を手札に抱える必要がある点の方が大きい気がしました。
2019/5/20 mtgの禁止制限改訂
2019年5月22日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
Pauper
禁止 噴出、ギタクシア派の調査、目くらまし
これを受けて、特に気になった点
ギタクシア派の調査は、とうとうヴィンテージでしか使えなくなってしまったんですね…
(というか、デザインミスといった方がいいのかも)
モダンでアロサウルス乗りが禁止にならなかったのは、アロサウルス乗りorその後の新生化や異界の進化を弾かれるリスクや、モダンホライゾンで否定の力(自分のターンでないなら、マナコストを支払う代わりに青のカード1枚を追放して撃てる否認)が収録されることを考慮したからでしょうか?
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0032539/
Pauper
禁止 噴出、ギタクシア派の調査、目くらまし
これを受けて、特に気になった点
ギタクシア派の調査は、とうとうヴィンテージでしか使えなくなってしまったんですね…
(というか、デザインミスといった方がいいのかも)
モダンでアロサウルス乗りが禁止にならなかったのは、アロサウルス乗りorその後の新生化や異界の進化を弾かれるリスクや、モダンホライゾンで否定の力(自分のターンでないなら、マナコストを支払う代わりに青のカード1枚を追放して撃てる否認)が収録されることを考慮したからでしょうか?
2019/1/21 mtgの禁止制限改訂
2019年1月22日 mtg-禁止改訂 コメント (2)詳しくはこちら
モダン
禁止 クラーク族の鉄工所
引用元の記事を見て、特に気になった点
>「アイアンワークス」デッキのカードを禁止する主な理由はその勝率とグランプリ・トップ8への進出率ですが、1ゲーム目(サイドボード前)の極端に高い勝率、時々ターンが長くかかること、複雑なルールの相互作用も副次的な要因として考慮しました。
>《クラーク族の鉄工所》があるゲームではマナ能力のタイミングに関する過剰に難解なルールの相互作用が必要になることがよく起こり、ゲームの状態を把握するためにはプレイヤーがそのことを理解する必要があります。これは、このデッキと対戦するプレイヤーや勝率が高いので使わないといけないと感じているプレイヤーにとっての、モダンへの参入障壁を作り出すことになりえます。
私が言っておきたいのは、「アイアンワークス」が直近のグランプリ・オークランドで活躍しましたが、単一のイベントの結果だけで禁止制限の決定は行われないということです。我々が行動を起こしたのは、「アイアンワークス」の去年1年間という長い期間を通しての実績によるものです。
→個人的には、クラーク族の鉄工所が禁止になったのは1ゲーム目の勝率が高いことよりも、第二の日の出が禁止になった時のように「コンボを始動するターンにかかる時間が長くなる」のが一番の理由だと思いました。
(もし1ゲーム目の勝率が高いだけで禁止になるなら、レガシーのコンボデッキのパーツの多くが禁止になりそうですし。ただ個人的にはアイアンワークスを相手にしたくなかったので、鉄工所が禁止になったのは歓迎しています)
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0031683/
モダン
禁止 クラーク族の鉄工所
引用元の記事を見て、特に気になった点
>「アイアンワークス」デッキのカードを禁止する主な理由はその勝率とグランプリ・トップ8への進出率ですが、1ゲーム目(サイドボード前)の極端に高い勝率、時々ターンが長くかかること、複雑なルールの相互作用も副次的な要因として考慮しました。
>《クラーク族の鉄工所》があるゲームではマナ能力のタイミングに関する過剰に難解なルールの相互作用が必要になることがよく起こり、ゲームの状態を把握するためにはプレイヤーがそのことを理解する必要があります。これは、このデッキと対戦するプレイヤーや勝率が高いので使わないといけないと感じているプレイヤーにとっての、モダンへの参入障壁を作り出すことになりえます。
私が言っておきたいのは、「アイアンワークス」が直近のグランプリ・オークランドで活躍しましたが、単一のイベントの結果だけで禁止制限の決定は行われないということです。我々が行動を起こしたのは、「アイアンワークス」の去年1年間という長い期間を通しての実績によるものです。
→個人的には、クラーク族の鉄工所が禁止になったのは1ゲーム目の勝率が高いことよりも、第二の日の出が禁止になった時のように「コンボを始動するターンにかかる時間が長くなる」のが一番の理由だと思いました。
(もし1ゲーム目の勝率が高いだけで禁止になるなら、レガシーのコンボデッキのパーツの多くが禁止になりそうですし。ただ個人的にはアイアンワークスを相手にしたくなかったので、鉄工所が禁止になったのは歓迎しています)
2018/11/26 mtgの禁止制限改訂
2018年11月27日 mtg-禁止改訂2018/8/20 mtgの禁止制限改訂
2018年8月21日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
結果:全フォーマットで変更なし
前回の禁止改訂以来、どこかの環境を破壊したという話を聞かなかったので、この判断も妥当だとは思いましたが、いい加減レガシーで精神錯乱ぐらいは解禁してもいいのではないかとは思いました。
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0030990/
結果:全フォーマットで変更なし
前回の禁止改訂以来、どこかの環境を破壊したという話を聞かなかったので、この判断も妥当だとは思いましたが、いい加減レガシーで精神錯乱ぐらいは解禁してもいいのではないかとは思いました。
2018/7/2 mtgの禁止制限改訂
2018年7月3日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
レガシー
禁止 死儀礼のシャーマン、ギタクシア派の調査
死儀礼について書かれた記事の中で、特に気になった点
>《死儀礼のシャーマン》の強力なマナ供給能力があれば、これらのデッキは普通に4色をプレイし、この環境で最も強力なカードを選ぶことができていました。この柔軟な能力はそれらのデッキがアグレッシブとコントロールのスタンスを簡単に切り替えられるようにして、それらを攻めることを難しくしました。
→以前から4cレオヴォルドやグリクシスDelverを始めとした、死儀礼デッキが幅を利かせていたのは分かりきっていたはずなので、禁止にするならなぜもっと前から禁止にしなかったのか不思議に思いました。
(黒1マナでも出せて、墓地の土地を追放してマナブースト・墓地のインスタントかソーサリーを追放して対象を取らない2点ライフロス・墓地のクリーチャーを追放して2点ゲインと後半に引いても役に立つ能力を持つ上に、1/2かつエルフと優秀なサイズと種族も併せ持つ死儀礼が禁止されたのはありがたかったです。とはいえ除去を撃てばまず落とせるので、禁止になるとは思ってませんでしたが)
ギタクシア派の調査について書かれた記事の中で、特に気になった点
>このカードはMagic Onlineで最もプレイされている2つのデッキ、「グリクシス・デルバー」と「ANT」の成功における主な要素になっています。《ギタクシア派の調査》はこれらやその他のデッキに、マナの支払いを必要とすることなく、急速に墓地を満たしたり呪文を唱えた数や引いたカードの枚数を考慮する能力を大きく強化したりしました。
>加えて、《ギタクシア派の調査》がもたらす情報のアドバンテージのコストは軽すぎます。
→若き紅蓮術士・陰謀団式療法・僧院の導師・炎の中の過去あたりとのシナジー形成、ストーム稼ぎ、感染やコンボデッキで仕掛ける前の前方確認が2点払うだけでアドバンテージを失うことなく行えてしまうとはいえ、禁止にすべきだとは思ってなかったので、正直驚きました。
死儀礼の禁止によって、3色以下の組み合わせのデッキが大多数になると同時に、墓地利用のデッキが増えてくると思います。
おまけ
せっかく4枚揃えた燃え立つ調査が、(相手にも無作為3枚ディスカードを強いるせいで)モダンで禁止になるのではないかと不安に思っていたので、禁止にならないと知ってホッとしました。
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0030750/
レガシー
禁止 死儀礼のシャーマン、ギタクシア派の調査
死儀礼について書かれた記事の中で、特に気になった点
>《死儀礼のシャーマン》の強力なマナ供給能力があれば、これらのデッキは普通に4色をプレイし、この環境で最も強力なカードを選ぶことができていました。この柔軟な能力はそれらのデッキがアグレッシブとコントロールのスタンスを簡単に切り替えられるようにして、それらを攻めることを難しくしました。
→以前から4cレオヴォルドやグリクシスDelverを始めとした、死儀礼デッキが幅を利かせていたのは分かりきっていたはずなので、禁止にするならなぜもっと前から禁止にしなかったのか不思議に思いました。
(黒1マナでも出せて、墓地の土地を追放してマナブースト・墓地のインスタントかソーサリーを追放して対象を取らない2点ライフロス・墓地のクリーチャーを追放して2点ゲインと後半に引いても役に立つ能力を持つ上に、1/2かつエルフと優秀なサイズと種族も併せ持つ死儀礼が禁止されたのはありがたかったです。とはいえ除去を撃てばまず落とせるので、禁止になるとは思ってませんでしたが)
ギタクシア派の調査について書かれた記事の中で、特に気になった点
>このカードはMagic Onlineで最もプレイされている2つのデッキ、「グリクシス・デルバー」と「ANT」の成功における主な要素になっています。《ギタクシア派の調査》はこれらやその他のデッキに、マナの支払いを必要とすることなく、急速に墓地を満たしたり呪文を唱えた数や引いたカードの枚数を考慮する能力を大きく強化したりしました。
>加えて、《ギタクシア派の調査》がもたらす情報のアドバンテージのコストは軽すぎます。
→若き紅蓮術士・陰謀団式療法・僧院の導師・炎の中の過去あたりとのシナジー形成、ストーム稼ぎ、感染やコンボデッキで仕掛ける前の前方確認が2点払うだけでアドバンテージを失うことなく行えてしまうとはいえ、禁止にすべきだとは思ってなかったので、正直驚きました。
死儀礼の禁止によって、3色以下の組み合わせのデッキが大多数になると同時に、墓地利用のデッキが増えてくると思います。
おまけ
せっかく4枚揃えた燃え立つ調査が、(相手にも無作為3枚ディスカードを強いるせいで)モダンで禁止になるのではないかと不安に思っていたので、禁止にならないと知ってホッとしました。
2018/4/16 mtgの禁止制限改訂
2018年4月18日 mtg-禁止改訂詳しくはこちら
結果:全フォーマットで変更なし
神ジェイスがモダン環境を破壊しなかったことや、個人的には禁止してほしかったレガシーでの死儀礼がほとんどの除去で対策できることを考えたら、この判断も妥当だと思いました。
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0030500/
結果:全フォーマットで変更なし
神ジェイスがモダン環境を破壊しなかったことや、
1 2